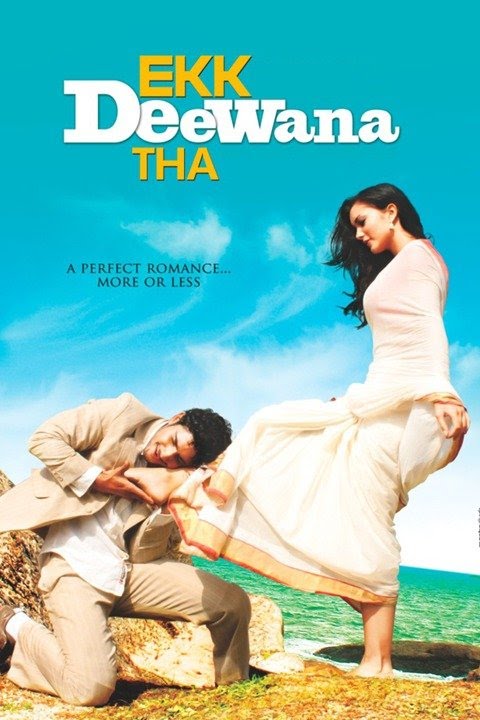
「Rehnaa Hai Terre Dil Mein」(2001年)という映画があった。ディーヤー・ミルザーのデビュー作、マーダヴァンの本格ヒンディー語映画デビュー作、そしてサイフ・アリー・カーンが脇役出演のロマンス映画で、個人的には結構好きだったがあまりヒットしなかった。当時はまだマルチプレックスがあまり普及しておらず、単館にて1日4ショー――モーニング、アフタヌーン、イブニング、ナイト――が基本だった。「Rehnaa Hai Terre Dil Mein」では変わったことをしており、エンディングに流れるボーナストラックのアレンジとそのダンスシーンをショーごとに違うものにしていた。もちろん、いくらインド映画好きでもそれら全てを鑑賞しに行くほどではなかったのだが、サウンドトラックにはそれらが全て収められており、自分が見たもの以外はどんな感じか勝手に想像を巡らせていたのを覚えている。
その映画の監督がガウタム・ヴァースデーヴ・メーナンであった。元々はタミル語映画の監督で、ヒンディー語映画「Rehnaa Hai Terre Dil Mein」の失敗の後、しばらくヒンディー語映画界からは離れていた。しかしあれから10年の時を経て再びヒンディー語映画に挑戦。それが本日(2012年2月17日)公開の「Ekk Deewana Tha」である。自身のタミル語ヒット作「Vinnaithaandi Varuvaayaa」(2010年)のリメイクで、またも変わった試みをしている。エンディングを2つ用意しているのである。ハッピーエンディングの通常版「Ekk Deewana Tha」と、サドエンディングの「Ekk Deewana Tha (Director’s Version)」である。しかしながら、上映館数は圧倒的に前者の方が多く、しかも後者を上映する映画館はどれもチケット代の高い最高級映画館ばかりなので、インド人の観客がハッピーエンディング版を選ぶのかサドエンディング版を選ぶのか、つまりインド人は実のところハッピーエンディングが好きなのかサドエンディングが好きなのか、その比較は無意味だ。もしこの映画を観るならば、ほとんどの観客が通常版を選ぶことだろう。僕が観たのもハッピー・エンディングの通常版である。
もうひとつ特殊なのは、英国人女優エイミー・ジャクソンをインド人ヒロインに起用していることだ。ミス・ティーン・ワールド(2008年)やミス・リバプール(2009年)の栄冠に輝いているが、彼女は特にインド系という訳でもない。ただ、タミル語映画「Madrasapattinam」(2010年)において主役の英国人女性役で出演し好評を博しており、既に南インド映画界では名の知れた存在のようだ。よって、今回はヒンディー語映画デビューとなる。そういえば「Love Aaj Kal」(2009年)でブラジル人女優ジゼル・モンテイロをインド人役に起用したことがあったが、サブヒロインの扱いであった。エイミー・ジャクソンが本作で演じるジェシーは正真正銘のメインヒロインであり、完全なるインド人女性の役である。南アジア人の血が入っていない女優がインド人役のメインヒロインを務めるのはこれが初のことではなかろうか。ちなみに主演男優はプラティーク・バッバルである。
また、キャストにあまりアピール力がないと判断したのか、音楽監督のARレヘマーンと作詞のジャーヴェード・アクタルの名前が大々的に宣伝されており、「ARレヘマーンとジャーヴェード・アクタルのミュージカル」とされている。これも異例の措置だと言える。
監督:ガウタム・ヴァースデーヴ・メーナン
制作:ガウタム・ヴァースデーヴ・メーナン、レーシュマー・ガターラー、ヴェーンカト・ソーマスンダラム、エルドレッド・クマール、ジャヤラマン
音楽:ARレヘマーン
歌詞:ジャーヴェード・アクタル
衣装:ナーリニー・シュリーラーム
出演:プラティーク・バッバル、エイミー・ジャクソン、マヌ・リシ、サチン・ケーデーカル、サマンサ・ルース・プラブ、バーブー・アントニー、ラメーシュ・スィッピー(特別出演)
備考:PVRプリヤーで鑑賞、通常版。
ムンバイー在住のサチン(プラティーク・バッバル)は機械工学を修めたものの、映画監督になる夢を追い掛けており、現在無職だった。師と仰ぐカメラマンのアナイ(マヌ・リシ)が有名監督ラメーシュ・スィッピー(本人)から仕事がもらえたため、一緒に仕事をすることになる。 ところでサチンは借家に住んでいたが、彼は大家の娘ジェシー(エイミー・ジャクソン)に一目惚れしてしまった。しかしサチンがヒンドゥー教徒であるのに対し、ジェシーはマラヤーリー・クリスチャン、しかも1歳年上であった。サチンの姉は、この恋に勝ち目はないから早めに諦めるように言うが、サチンは聞かなかった。 サチンはジェシーの前に出ると緊張してしまって挙動不審になったが、それでも姉の助けもあってジェシーと会話を交わせるようになる。そして出会って10日でサチンはジェシーに愛の告白をしてしまう。ジェシーからは返事をもらえなかった。しかもその日ジェシーは家に帰って来なかった。調べてみるとジェシーは祖父母の住むアレッピーへ帰ってしまっていた。サチンはジェシーの後を追い掛け、アナイを連れてケーララ州まで飛んで行く。 全く手掛かりがなく、ジェシーを見つけるのは困難だった。しかしジェシーがキリスト教徒であることを思い出し、日曜日にアレッピーで一番大きな教会へ行ってみる。するとそこでジェシーと再会することができた。ジェシーは祖父母にサチンをクラスメイトだと紹介する。祖父母は彼らを家に招く。帰り際にサチンはジェシーにいきなり告白してしまったことを謝る。ジェシーはまずは友達になろうと提案し、2人は友達となる。 ジェシーはアレッピーからムンバイーへ列車で戻ることになっていた。サチンはわざとジェシーと同じ列車を予約し、一緒にムンバイーへ行くことにする。その列車の中で2人はキスをする。 ところが、ジェシーの兄ジェリーが二人の仲を疑うようになる。サチンはジェリーを殴ってしまい、ジェリーは仲間を連れてサチンを脅しにやって来る。この事件によってサチンとジェシーの仲がお互いの両親にばれてしまう。ジェシーの父親はサチンの家族を追い出そうとするが、サチンの父親も売り言葉に買い言葉で最大限居座ることを宣言する。そこでジェシーの父親はジェシーをすぐに結婚させてしまうことにする。家族はジェシーを連れてアレッピーへ行ってしまう。 それを知ったサチンは再びジェシーを追ってアナイと共にアレッピーまで行く。ジェシーと再会した教会でジェシーの結婚式が行われようとしていた。サチンとアナイは参列者に紛れ込んで宣誓の儀式を見守る。するとジェシーは宣誓を拒否し、式場から逃げ出してしまう。また、ジェシーはそのときサチンがいるのに気付く。サチンとアナイは一度式場から抜け出すが、ジェリーに見つかってしまい、乱闘になってしまう。そこへ警察が駆けつけ、サチンとアナイは警察署に連行される。ジェシーに頼まれた父親は2人を訴えないことにするが、2人に対し二度と目の前に現れないように警告する。 ところがサチンは諦めが付かなかった。夜中こっそりジェシーの家に忍び込み、彼女と出会う。ジェシーは今までの気持ちを吐露し、彼女もサチンに一目惚れしていたことを明かす。満足したサチンはとりあえずムンバイーへ帰る。 ムンバイーに戻った後、サチンの家族は引っ越しをするが、サチンとジェシーはデートを繰り返していた。しかし、ラメーシュ・スィッピー監督のロケが始まり、サチンはアシスタントとして忙しいが充実した毎日を送るようになる。一方、ジェシーは父親から結婚を強要され続けており、フラストレーションを感じていた。ジェシーは何度もサチンに電話を掛けるが、マンガロールにロケに出掛けていたサチンとはなかなか会話が成立しなかった。ジェシーから強く呼び出しを受けたサチンはラメーシュ・スィッピー監督から許可をもらって一時的にムンバイーに戻るが、ジェシーは既にサチンと別れることを決意していた。サチンが何を言っても無駄だった。その後ジェシーはサチンに何も告げずに英国へ渡ってしまう。姉の情報では、彼女は既に結婚してしまったとのことだった。 こうして2年の月日が過ぎ去った。サチンはまだジェシーのことを諦め切れていなかったが、彼に一途に恋する女性が現れ、迷っていた。ある日サチンはジェシーとのロマンスを題材に脚本を書き始める。脚本は完成し、プロデューサーも決まり、サチンはとうとう監督デビューする。サチンがタージマハルでロケを行っていたところ、そこに偶然ジェシーが現れる。2人は思い出話に花を咲かせる。その会話の中でサチンは今でもジェシーのことを愛していることを明かす。実はジェシーも結婚していなかった。英国に行った後、すぐにインドに戻り、デリーに住んでいたのだった。サチンとジェシーはすぐにでも結婚することを決め、デリーの教会と寺院で婚姻の儀式をする。 サチンの映画「Jessie」も完成し、公開される。サチンとジェシーはそれを一緒に観る。アナイは映画が大ヒットになっていると報告する。
タミル語ロマンス映画のリメイクであることが影響しているのだろう、ヒンディー語映画のトレンドから見たら古風でワンパターンな映画であった。もちろん、「Agneepath」(2012年)の成功からも分かるように、古風な映画作りをリバイバルすることがそのまま失敗作につながる訳ではない。現代向けに、上手に丁寧にアレンジすれば素晴らしい映画になり得る。だが、「Ekk Deewana Tha」は到底そのレベルに達していなかった。昨今のヒンディー語映画界ではめっきり減ったストレートなロマンス映画ということで、かえって心に直接響く部分もあったのだが、映画が進行するに従い、結局はインドの伝統的ロマンス映画の焼き直しに過ぎないということが明らかになって来る。
もっとも腑に落ちなかったのは、いまどき宗教やコミュニティーの違いを恋愛・結婚の障壁として前面に出していたことである。サチンはマハーラーシュトラ州沿岸部に多いコーンカニー・ブラーフマン、つまりヒンドゥー教徒。一方、ジェシーはケーララ州をベースとするマラヤ―リーのキリスト教徒。2人ともムンバイーで生まれ育っていながら、異なるコミュニティーに属する。確かにインドでは、出自の地域や宗教が違う男女の結婚は難しくなる。しかし、ヒンディー語映画界では、ヒーローとヒロインの恋愛成就の壁にそれらの要素を持って来ることは稀となった。もっと日本人の恋愛観に近い恋愛となって来ている。よって時代錯誤のロマンス映画に感じた。
また、劇中においてヒロインの方がヒーローよりも1歳年上であることも恋愛の障壁として何度も何度も明確に提示されていた。これも古めかしく感じた。やはり、インドでは花婿より花嫁の方が年上ということは稀だ。しかし、ヒンディー語のロマンス映画でそれが明示され問題になったことは今まであまり記憶にない。その一方で極端な例――例えば女性の方が一回りも二回りも年上――のヒンディー語映画は過去にいくつかあり、もっとも有名なのは「Dil Chahta Hai」(2001年)や「Leela」(2002年)である。
また、ヒンディー語映画では、ヒーローが一目惚れしたヒロインをストーカーの末になぜかゲットするような、単純かつはた迷惑なロマンス映画は下火となっている。「Ekk Deewana Tha」は正にそのパターンで頭痛がした。
おそらく南インド映画ではまだこれらのタブーやパターンを軸に恋愛映画を作る習慣が残っているのであろう。それらをそのままヒンディー語映画に当てはめてしまったのがこのリメイク映画の大きな失敗だと言える。
また、展開に意外性がない割には唐突なまとめ方がされており、雑な印象を受けた。ジェシーが結婚式の宣誓で「ノー」と言うのは容易に予想できるし、彼女が最後に「実は結婚していない」と明かすのもインド映画の常套手段だ。その割に、二人が勝手に結婚して、ジェシーの父親に挨拶しに行く重要なシーンは曖昧に終わらせられており、面倒を避けたと揶揄されても仕方ないだろう。主役2人の恋愛の進展もどこか現実感や説得力がなく、ロマンス映画としては失格だった。
多くの欠点を持ちながらも、ARレヘマーンの音楽はいくつか素晴らしいものがあり、映画の救援に駆けつけていた。「Kya Hai Mohabbat」、「Aromale (My Beloved)」、「Hosanna」、「Phoolon Jaisi」など、いい曲が揃っている。サントラCDには10曲収録されている。いくつかは南インド的なダンスと共に使われていた。しかし、どうもたくさん注文し過ぎてしまったようで、全てが効果的に劇中で使われていたとは言えなかった。ちょっとだけ申し訳程度に流れてすぐにカットされてしまった曲もあった。
ところで、インド映画では宗教的マイノリティーがステレオタイプなイメージと共に描写されることが多い。その中でもキリスト教徒はかなり明確なステレオタイプがある。西洋文化にどっぷり染まってインド精神から遠い存在で、酒を飲み、肉を食べ、性にオープンで、家でも英語をしゃべるなど、そういうキャラクターとして描写されやすい。しかし「Ekk Deewana Tha」のジェシーやその家族は、確かにキリスト教徒だったものの、よりマラヤーリーとしての文化を強く保持しており、現実のインド人キリスト教徒に近い気がした。それもそのはず、ガウタム・ヴァースデーヴ・メーナン監督はケーララ州出身であり、この正確な描写も納得である。
主演プラティーク・バッバルは最近絶好調だ。「Jaane Tu… Ya Jaane Na」(2008年)の脇役出演で注目を浴び、2011年には「Dhobi Ghat」から「My Friend Pinto」まで様々な作品に出演している。母スミター・パーティール似の寄り目の顔が特徴で、気弱な男が一番似合う。「Ekk Deewana Tha」での彼の役は多少混乱していた。ジェシーの前では挙動不審男なのだが、いきなり愛の告白をしたり、ジェシーを追い掛けてケーララ州まで行ったり、思い切った行動に出ることもある。さらにジェシーの兄を大した理由もなくいきなり殴るなど、喧嘩っ早い一面も見せており、謎の性格であった。おそらく脚本からこういう設定だったのだろうが、それを演技力で包括するところまで行っていなかったのも、その現実感のなさの一因であろう。
エイミー・ジャクソンは英国人ながら意外にインド人に見え、その点で不満はなかった。台詞はおそらく全て吹き替えであろう、かなり低い声なのだが、それがまたなかなか冷たい表情と合っていて良かった。わざわざ英国人女優をインド人役に起用する必要があるのか、それは大きな疑問であるが、少なくともこの「Ekk Deewana Tha」に関する限りは悪くはなかった。
脇役陣の中では、サチンの師匠であり良き相談役であるアナイを演じたマヌ・リシが非常に良かった。アルシャド・ワールスィー的なベラベラッというしゃべり方をするのだが、それが粋だった。また、どういう縁か、「Sholay」(1975年)で知られる映画監督ラメーシュ・スィッピーが特別出演している。劇中で「Sholay」の賞賛があったり、まるで彼に捧げられた映画のようになっていた。
基本的に舞台はムンバイーであるが、ジェシーの実家の関係でケーララ州アレッピー(現在の正式名称はアーラップラ)が何度か登場したり、サチンとジェシーの再会の場として、ベタだが、アーグラーのタージマハルが出て来たりする。映画中ではあまり明確に言及されていないが、デリーでもかなりロケが行われている。二人が結婚したのはオールドデリーのセント・ジェームス教会だし、結婚後に2人がデリー観光として訪れた場所の中には、一瞬だけの登場だったが、インド門、ディッリー・ハート、バサントローク・マーケットなどが含まれていた。
言語は基本的にヒンディー語であるが、ジェシーがマラヤーリーということもあり、マラヤーラム語の台詞も時々聞こえて来る。それらには大体英語とヒンディー語の字幕が付く。
「Ekk Deewana Tha」は、先週公開の「Ek Main Aur Ekk Tu」(2012年)に続きロマンス映画であるが、どうもどちらもいまいちだ(なぜか題名も似ている)。エンディングを2つ用意するというのはかなり珍しい試みであるが、一般向けのハッピーエンディング版がこの出来だと、より高価かつレアな方のバージョンの出来はさらに心配である(観る予定もない)。ただ、ARレヘマーンとジャーヴェード・アクタルの手による楽曲は一定のレベルにあり、それが映画を何とか沈没から救っている。それでも完全浮上とまではいかないだろう。
