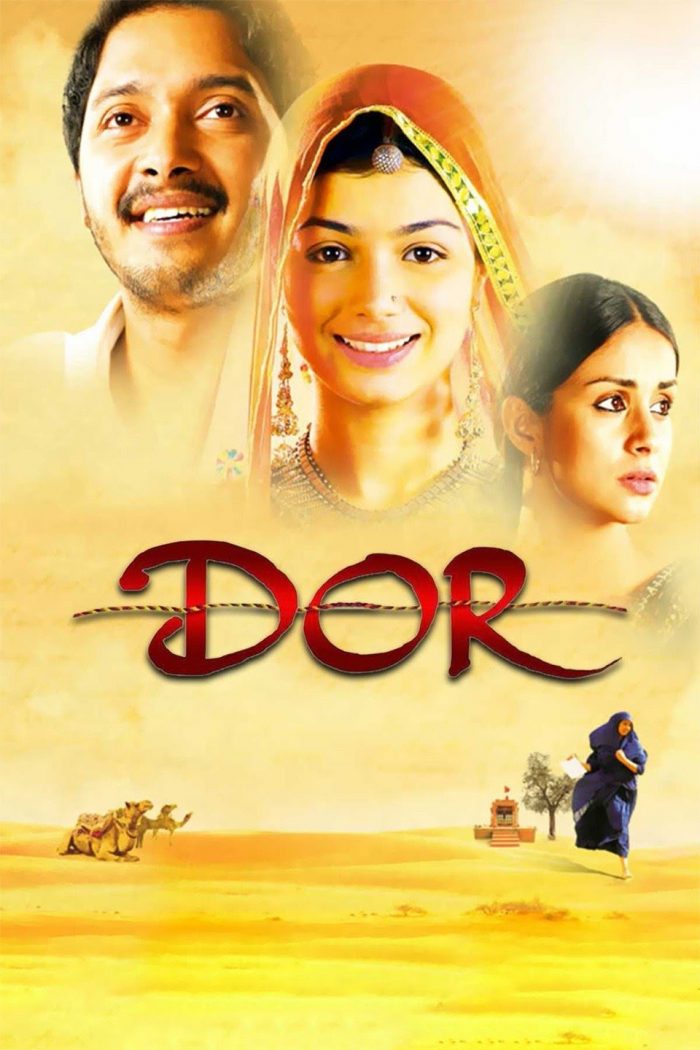
インドはお祭りシーズンに突入し、街はだいぶ騒がしくなった。先週中頃から調子を崩してしばらく寝込んでいたが、やっと復活したので映画を観に出掛けた。最近1週間に3、4本の映画が公開されるので追いつけていない。今日観た映画は、2006年9月22日から公開の新作ヒンディー語映画「Dor」である。
「Dor」とは元々「紐」という意味だが、転じて「結び付き」のような意味がある。監督はナーゲーシュ・ククヌール、音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、アーイシャー・ターキヤー、シュレーヤス・タルパデー、グル・パナーグ、ギリーシュ・カルナド、ルシャド・ラーナー、アニルッド・ジャートカル、ナーゲーシュ・ククヌール(カメオ出演)など。
ヒマーチャル・プラデーシュ州に住むムスリムの女性ズィーナト(グル・パナーグ)は、サウジアラビアに出稼ぎに出掛けた夫アーミル(ルシャード・ラーナー)からの音信を楽しみにして生きていた。ところがある日電話があり、アーミルが殺人の容疑で逮捕されたとの連絡を受ける。サウジアラビアで同居していたインド人シャンカル(アニルッド・ジャートカル)が階上から転落して死亡したのだが、アーミルが故意に突き落としたとされていた。そしてアーミルは裁判所から死刑を宣告された。だが、ズィーナトはそれが事故であり、アーミルは無罪であることを確信していた。アーミルを救う手がひとつだけあった。サウジアラビアの法律では、死者の妻が犯人を許せば、死刑は免れるのであった。タイムリミットは2ヶ月。ズィーナトは、シャンカルの妻を探す旅に出る。 シャンカルはラージャスターン州出身であった。ズィーナトの手元には、アーミルとシャンカルが共に写った一枚の写真だけがあった。だが、それ以上の情報はなかった。親切なスィク教徒のトラック運転手にラージャスターン州まで連れて来てもらったズィーナトは、そこから一人でシャンカルの妻を探し出す。そのとき彼女は、ベヘルーピヤー(シュレーヤス・タルパデー)という怪しい男と出会う。ベヘルーピヤーは最初、ズィーナトのバッグを盗んで逃げるが、ズィーナトの身の上を知り、彼女にバッグを返すと同時に、シャンカルの妻捜索を手伝うことにする。 写真の中の一部にジョードプルの風景が写った写真を見つけ、二人はジョードプルへ向かう。ジョードプルでさらに詳しい情報が手に入り、ズィーナトは遂にシャンカルの妻が住む家に辿り着く。 シャンカルの父親(ギリーシュ・カルナド)は、借金の抵当として差し押さえられた先祖代々のハヴェーリー(邸宅)を買い戻すことだけを考えて毎日暮らしていた。そのためにシャンカルをサウジアラビアに出稼ぎに送ったのだった。だが、シャンカルは死んでしまい、夢はあと一歩のところで水泡に帰してしまった。シャンカルの妻ミーラー(アーイシャー・ターキヤー)も、夫の死により人生が180度変わってしまい、悲しみに沈む毎日を送っていた。ズィーナトは父親に出会い、ズィーナトのサインを求めるが、シャンカルの母親は息子を殺した男の妻を呪い、彼女に唾を吐いて追い返す。 それでもズィーナトは諦めなかった。ミーラーが週に一回寺院へ通っているのを知り、寺院で彼女と会って、友情を深めることにする。まずはアーミルのことは黙っていた。二人は急速に親しくなり、ミーラーも自立して生きる喜びを知り始める。だが、ズィーナトは次第にアーミルのことを切り出しづらくなってしまう。そのとき、アーミルに死刑執行の日が2日後に迫っていることが知らされる。ズィーナトは遂に自分の正体を明かし、彼女に書類にサインしてくれるよう頼む。だが、ミーラーはズィーナトに裏切られたことにショックを受け、サインを拒否する。 意気消沈し、駅で列車を待つズィーナト。一方、ミーラーは自分の行動を制限しようとした上、彼女を実業家の男に売り渡そうとしていた父親と対立し、部屋に閉じ込められてしまっていた。だが、彼女を励ましたのは、同じく未亡人だった祖母であった。祖母はミーラーを解放し、ズィーナトのところへ行くよう促す。駅へ走ったミーラーは、走り出した列車の中に座っていたズィーナトに書類を渡す。ズィーナトはミーラーに手を差し伸べる。ミーラーも走り出し、列車に飛び乗る。
ナーゲーシュ・ククヌール監督というと、「Hyderabad Blues」(1998年)や「Iqbal」(2005年)などの良質な映画を作ることで有名な映画監督である。この「Dor」もククヌール監督が脚本・監督を担当しており、期待度は非常に高かった。だが、結論から先に言うと、期待していたほどいい映画でもなかった。
映画のテーマはインドの女性問題と言っていいだろう。よって、女性が主人公の映画であった。ミーラーはラージャスターン州に住む伝統的な女性、ズィーナトはヒマーチャル・プラデーシュ州に住む先進的な考えを持った女性である。この全く対照的な二人の女性の夫が、出稼ぎ先のサウジアラビアで出会い、事件に巻き込まれてしまう。ミーラーの夫は死に、ズィーナトの夫は殺人罪により死刑を宣告される。だが、サウジアラビアの法律では、犠牲者の妻が犯人を許せば、犯人は刑を免れることができるようだ。ズィーナトは、ミーラーの許しを得るため、彼女を探す旅に出る。これが物語の導入部である。
ズィーナトの人物背景はそれほど詳しく描写されていなかった一方、ミーラーを取り巻く問題はよく描写されていた。インドにおける未亡人の地位の低さは度々問題として取り上げられる。伝統的に、未亡人は一切の装飾品を身に着けてはならず、世俗的な快楽から隔離された生活を一生強いられる。映画中では、ミターイー(甘いお菓子)すら食べるのに許可が要ることが取り上げられていた。また、未亡人は不吉な存在とされるため、未亡人になった途端、誰も彼女に触れようとして来なくなった。若さの絶頂にあるミーラーにとって、このような環境は生き地獄以外の何者でもなかった。この映画が何らかの社会問題を提起しているとしたら、それはミーラーに代表されるだろう。
そして、そのミーラーに自立の道を説くのがズィーナトの役割であった。ズィーナトは、決定は自分でするべき、そしてその決定の責任も自分で負うべき、という人生の金言をミーラーに説き続ける。ズィーナトとの友情は、いつしかミーラーの顔に笑顔を戻す。その友情は、ズィーナトがアーミルとシャンカルのことを打ち明けることにより一旦壊れてしまうが、それでもミーラーは最後にはズィーナトを受け入れる。
映画としては一応まとまっていた。クライマックスのシーン、走り出す列車を追いかけるシーンは非常に陳腐ではあったが、映画の終わり方としては盛り上がりがあり、悪くはなかった。しかし、ミーラーが体現していたインドの未亡人問題を、女の友情の復活という出来事でまとめて終わらせてしまったことで、問題の焦点がぼやけてしまっていた。また、社会問題を根底まで分析していたとも思えなかった。結果として、非常に表層的で中途半端な映画になってしまっていた。これは「Iqbal」でも感じたことである。
ヒマーチャル・プラデーシュ州の雄大な山景色と、ラージャスターン州の広大な砂漠の対比は素晴らしかった。どちらも素晴らしく、実際に旅したこともあるので、さらに感慨は深いものがあるのだが、どういうわけか、僕はラージャスターン州の風景により心を惹かれた。どこまでも続く青い空と黄金の砂漠、素朴な家屋と古びたハヴェーリー(邸宅)、そして住民たちの原色を基調としたカラフルなターバンや衣服・・・これらの要素のミックスが、横長のシネスコのスクリーンに非常によく映えるのである。映画館とラージャスターンはどうしてこうも相性がいいのだろうか?
映画中、一際目立っていたのはズィーナト役のグル・パナーグ。1999年のミズ・インディア・ユニバースである彼女は、これまで数本の映画にしか映画に出演していなかったものの、かなり本格的な演技力を発揮していた。だが、どうも彼女がしゃべる正統派のウルドゥー語は、吹き替えのようだ。プロデューサーの一人、イラーヒー・ヘープトゥッラーが吹き替えを担当したらしい。
もう一人のヒロイン、アーイシャー・ターキヤーは場違いな印象を受けた。彼女の柔和な顔や華奢な体型は都会のモダンガールそのもので、ラージャスターン州の片田舎に住む女の子の役は違和感があった。演技からもヒロイン臭が抜け切れておらず、映画に溶け込めていなかった。彼女はこういうちょっと社会派風映画に手を出さす、メインストリームの娯楽映画に集中すべきだ。それだけのチャンスと才能も彼女にはある。
「Iqbal」で一躍注目を浴びたシュレーヤス・タルパデーは、今回はさらにキャリアを伸ばしたと言っていいだろう。女性中心の映画だったため、活躍の場は限られていたし、映画の最後ではほぼ無視されてしまっていたが、登場シーン中で存分に自身の潜在力を引き出していた。「Iqbal」では言葉がしゃべれない役であったためセリフがなかったのだが、今回初めてセリフをしゃべり、しかもけっこうセリフでも観客を惹き付ける力を持った俳優であることを証明していた。
ナーゲーシュ・ククヌール監督が、村に工場を建設する実業家の役でカメオ出演していた。彼は、未亡人のミーラーに目を付け、父親に対し、借金の肩代わりをする代わりにミーラーを性欲処理用に送ってよこすように提案するという悪徳振りを見せていた。だが、ククヌール監督の演技ははっきり言って憎々しさに欠けていた。
「Dor」は、新時代のインド映画の一本と言える。マルチプレックスの普及により、インド映画には大きな変化が訪れている。その内のひとつが、娯楽映画と芸術映画の融合である。マルチプレックス登場前は、芸術映画が上映されるのはカルチャーセンターのような限定された場所か映画祭くらいしかなかったが、マルチプレックスはそれらの映画に一般の人々の目に触れるチャンスを作り出した。そして、けっこうな興行収入を上げる映画も出て来た。その影響により、都市部のマルチプレックスで上映することを目的とし、しかもある程度の興行収入を期待した芸術映画、社会派映画が作られるようになった。逆に、最初から都市部の中流階級層しかターゲットにしていないような新感覚の娯楽映画も作られるようになった。両者の境目は限りなく曖昧になって来ている。この新たな傾向は、いくつかの傑作を作り出したのだが、同時にどっちつかずの中途半端な駄作を生み出す結果にもなった。例えば、「Rang De Basanti」(2006年)は元々「Paint It Yellow」という題名で英語の社会派映画として制作が予定されていたのだが、途中でヒンディー語の娯楽映画路線に転換された。同映画は大ヒットし、社会にも大きな影響を与え、アカデミー賞外国語映画賞のインド代表作にも選ばれた。これは成功例と言っていいだろう。だが、残念ながらこの「Dor」は失敗作の一本に数えられる。ククヌール監督の前作「Iqbal」も僕は失敗作に近いと思っている。社会問題を提起する鋭い視点、問題の根源を追究する分析力、そしてそれを映画中で効果的に再構築する想像力に欠けた社会派映画が無意味に増えてしまっている。
総じて、「Dor」は、ヒマーチャル・プラデーシュ州とラージャスターン州の自然の対比が美しい作品であるが、テーマとして取り上げたインドの未亡人問題をほとんど棚上げにし、いかにも映画的にまとめて終わってしまっており、非常に中途半端な印象を受ける映画になってしまっていた。
