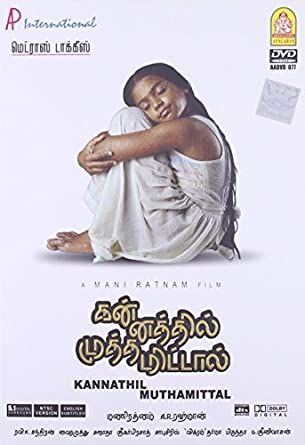
午前中授業に出て、午後からインド国際映画祭へ行き、リバティー・シネマで15:30から上映のマニ・ラトナム監督タミル語映画「Kannathil Muthamittal(ほっぺにキス)」を観た。2002年2月14日公開の映画である。音楽はARレヘマーン。主演はマーダヴァンやスィムランなど。どちらもタミル語映画界のスターである。
タミル・ナードゥ州チェンナイ。作家のティルチェルヴァン(マーダヴァン)とその妻インディラ(スィムラン)の間には3人の子供がいた。長女のアヌダ、長男のヴィナヤン、そして次男で末っ子のアキランだ。やんちゃな子供たちに手を焼きながらも、ティルチェルヴァンたちは幸せに過ごしていた。 アヌダの9歳の誕生日が来た。ティルチェルヴァンとインディラはアヌダに真実を打ち明ける決意をする。実はアヌダは二人の子供ではなく、孤児院で養子にした子供だった。それを知ったアヌダはショックを受け、心を閉ざしてしまう。そんなアヌダにティルチェルヴァンは、アヌダを養子にした過程を話す。 アヌダはスリランカからの難民で、シャーマーという名の女性の子供だった。彼女はラーメーシュワラムでアヌダを産んだ後、すぐにスリランカへ帰ってしまった。孤児院に入れられていたアヌダを見て、そのときちょうどラーメーシュワラムにいたティルチェルヴァンはインスピレーションを得て小説を書く。そしてその子を養子にすることを決意する。しかし独身の男性が養子をもらうことは法律上不可能だったため、恋人だったインディラと結婚し、養子をもらったのだった。つまり、アヌダが両親の結婚のきっかけとなったのだ。 自分がラーメーシュワラムで生まれたこと、そして母親の名前がシャーマーであることを突き止めたアヌダは、今までの自分の写真を一冊のアルバムに収め、両親には内緒でラーメーシュワラムへ旅立つ。アヌダが行方不明になったことを知った両親もすぐにラーメーシュワラムへ飛ぶ。アヌダはラーメーシュワラムでも母親の手掛かりをつかむことができなかった。海を眺めて佇むアヌダに、ティルチェルヴァンは優しく語り掛ける。「お父さんが絶対に母親に会わせてやるから。」 こうして、ティルチェルヴァン、インディラ、そしてアヌダはスリランカへ旅立った。そのときスリランカはゲリラと政府軍の戦いの真っ最中だった。3人は戦火の中をくぐり抜けつつ、アヌダの真の母親であるシャーマーを探す。そして遂にシャーマーの生まれ故郷の村に辿り着く。ティルチェルヴァンはシャーマーの兄と出会うことに成功し、公園で待ち合わせをする。しかしシャーマーはゲリラの一員となっていたのだった。 アヌダたちは公園でシャーマーを待った。しかしそのとき公園にやって来たのは軍隊だった。突然そこでゲリラと政府軍の銃撃戦が始まり、インディラは負傷してしまう。アヌダはインディラが負傷してしまったことに傷つき、もうインドへ帰ることにする。だが、インディラの要望により、約束の公園にもう一度だけ行ってみることにした。 公園は先日の銃撃戦で廃墟となっていた。そこへ一台のオートリクシャーが止まる。中からはシャーマーが出て来た。シャーマーとアヌダは、アヌダが生まれたとき以来の再会を果たす。アヌダはシャーマーに「チェンナイに来れば戦争もないよ」と言うが、シャーマーは「この国に平和が訪れたら必ず行くわ」と答える。アヌダは「それはいつ?」と聞く。しかしシャーマーは何も答えずに再びジャングルの中へ去っていくのだった。
まさにマニ・ラトナム監督らしい、社会問題に深く切り込みつつも娯楽性を盛り込んだ作品だった。スリランカのLTTE(タミル・イラーム解放の虎)を暗に題材にしているところがすごい。現在ではLTTEと政府の間で話し合いが持たれ、スリランカの治安もこの映画ほど酷くはないが。僕もこの前実際にスリランカに行ったが、何も怖い目に遭ったりしなかった。
インドの映画監督で、映像を見て一目で識別できる人は、マニ・ラトナムぐらいだという話を聞いたことがある。彼の映像には確かにインド人離れした独自の作家性を感じる。1コマ1コマに彼のサインが刻まれているかのようだ。敢えて荒を探すとしたら、全体的に淡々とした撮り方で、テロに遭遇するシーンや砲撃・銃撃を受けるシーンにおいてもそんな感じだったので緊張感に欠けていたところがあったことか。
ミュージックマスターの異名を持つARレヘマーンの音楽も、聞いて一耳で彼の音楽だと分かった。聞いていて気持ちのいい曲が多く、まるで耳から脳にかけて洗浄されるかのようだ。今回の作品で、彼の歌はミュージカルシーンで自然に挿入される形で使用されていることが多かった。タミル語映画特有の、突然脈絡なしに挿入されるダンスシーンもいくつかあったが、それは前半に固められており、ストーリーが重厚になる後半にそういうシーンが無造作に挿入されるような間違いがなくてホッとした。
アヌダを演じた子役の演技はとてもよかったと思う。マーダヴァンやスィムランはどちらかというと子役のサポート役のようなものだった。僕のマーダヴァンのイメージは「Rehnaa Hai Terre Dil Mein」(2001年)のガキ大将役で固定されていたので、かえって今回の彼の抑え気味の演技は新鮮だった。
僕の行ったことのあるラーメーシュワラムやコロンボの風景が映画中に登場したのも少し嬉しかった。スリランカのシーンは全てスリランカでロケされたか知らないが、見ていてまたスリランカに行きたくなった。ラーメーシュワラムの風景も実際以上にきれいに映っていた。
おそらく今回の映画祭でもっとも人入りがよかった映画ではないだろうか?少なくともバルコニー席はほぼ満員だった。やはりデリー在住タミル人らしき人が多かったみたいで、タミル語が飛び交っていた。隣に座っていたおじさんは、映画中の曲を口ずさんでいた。
